「開業届を出していないけど、PayPayは導入できるの?」
そんな疑問を持つ個人事業主は少なくありません。実は、開業届なしでも事業性を証明できればPayPayの加盟店審査は通る可能性があります。
本記事では、導入可否や審査のポイント、メリット・デメリット、確定申告までの流れをわかりやすく解説します。これからキャッシュレス対応を始めたい方は必見です。
PayPayをビジネスに導入するならこちら!
開業届なしでPayPayは利用できるのか?

・開業届がなくてもアカウント作成は可能?
・PayPayの登録条件と必要書類
・屋号なしの場合の登録方法
・個人事業主と副業利用の違い
・法的・税務上の注意点
開業届がなくてもアカウント作成は可能?
結論として、開業届を提出していなくてもPayPayの加盟店アカウントは作成できます。ただし「事業性」を証明できる資料が必要です。ネットショップのURL、SNS販売実績、名刺、商品の写真など、活動の証拠があれば審査に通る可能性は高まります。反対に「これからやります」というだけでは通りにくいです。
PayPayの登録条件と必要書類
PayPay加盟店登録には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、事業に関する情報が求められます。法人であれば登記簿謄本、個人事業主であれば開業届の控えが一般的ですが、開業届がない場合は事業用ホームページやショップページのURLなどが代替資料になります。
屋号なしの場合の登録方法
屋号がなくても本名で登録可能です。店舗名の欄には本名、またはネットショップの名称を入力すればOKです。ただし、店舗名はPayPay決済画面に表示されるため、顧客が安心できる名称を設定することが重要です。もし個人名を避けたい場合は、屋号を作り名刺やSNSに反映させるだけでも印象が良くなります。
個人事業主と副業利用の違い
副業の場合でもPayPay導入は可能です。例えば週末だけのイベント販売や、趣味を活かしたハンドメイド品の販売などでも審査は通るケースがあります。ただし、副業でも売上が一定額を超えれば確定申告が必要になりますので、その点は注意が必要です。
法的・税務上の注意点
開業届を出していないと税務署から正式な「個人事業主」とは見なされませんが、売上が発生すれば税務申告の義務はあります。PayPayは入金記録が残るため、税務署からの調査時にはすぐに売上履歴が確認されます。したがって、開業届なしで始めても、帳簿付けや領収書管理は必ず行いましょう。将来的に事業を拡大するなら、早めに開業届を出しておく方が税務上も有利です。
PayPayを導入するメリットとデメリット

・キャッシュレス決済の普及状況
・売上アップにつながるポイント
・PayPayキャンペーン活用術
・手数料・振込サイクルの特徴
・デメリットやリスクも
キャッシュレス決済の普及状況
近年、日本国内でキャッシュレス決済の利用率は年々上昇しています。経済産業省のデータによると、2023年にはキャッシュレス比率が36%を超え、2030年には40%超を目指すとされています。その中でもPayPayは圧倒的なシェアを誇り、登録者数は6,000万人を突破。スマホ1つで決済ができる手軽さから、小規模店舗や個人事業主の導入も急増しています。
キャッシュレスの普及は、現金払いを好む層にも少しずつ浸透しており、「現金しか使えない店」より「PayPay対応店」を選ぶ消費者も増えています。特に若年層やスマホ世代は、現金を持ち歩かない傾向が強く、PayPay対応は集客面での大きなメリットになります。
さらに、感染症流行時には「非接触決済」が安全性の面からも評価され、利用者が一気に増えました。こうした流れは今後も続くと考えられ、PayPayはもはや“あると便利”ではなく“ないと不便”なサービスになりつつあります。個人事業主にとっては、時代の流れに合わせて顧客のニーズに応える手段として、導入の価値は非常に高いといえます。
売上アップにつながるポイント
PayPayを導入すると、現金派ではない顧客層も取り込めるため、売上アップにつながる可能性が高まります。特に、PayPayユーザーは「PayPayが使えるお店」をアプリ内で検索できるため、対応店舗であること自体が新規顧客の集客ポイントになります。
さらに、PayPayは不定期に「ポイント還元キャンペーン」や「地域振興キャンペーン」を実施しており、これらを活用すれば集客効果は倍増します。例えば、特定の地域で「最大20%還元」などの施策が行われると、その期間はPayPayユーザーが積極的にお店を訪れやすくなります。実際に、こうしたキャンペーン期間中に売上が2〜3倍になったという事例も少なくありません。
また、少額決済でも手間なく受けられるため、「100円のコーヒー」や「ちょっとした雑貨」など低単価商品の販売でも決済スムーズ化による購買促進が期待できます。現金払いでは小銭のやり取りで時間がかかる場面も、PayPayなら即時決済。これにより回転率も上がります。
一方で、PayPay残高払いは現金支払いより心理的ハードルが低く、「ついで買い」や「まとめ買い」が起きやすいという傾向があります。結果として客単価が上がる可能性も高いです。この心理効果はリアル店舗だけでなく、ネット販売やイベント出店でも有効です。
つまり、PayPay導入は単なる決済手段の追加ではなく、集客・客単価アップ・販売機会の拡大を同時に狙える戦略的ツールといえます。
PayPayキャンペーン活用術
PayPay最大の魅力の一つが、強力なキャンペーン施策です。特に加盟店側として押さえておきたいのは、「全国規模のキャンペーン」と「自治体連携型キャンペーン」の2種類。
全国規模では、過去に「最大20%還元」や「100億円あげちゃうキャンペーン」など大型施策が実施され、利用者数を爆発的に増加させました。これらの施策はPayPay本体が費用を負担するため、加盟店側の負担はゼロ。参加登録をするだけで恩恵を受けられます。
自治体連携型は、各市区町村が地域経済活性化を目的として実施するもので、「PayPayで支払うと最大30%還元」などの内容が多いです。特定エリアでビジネスをしている個人事業主には非常に効果的で、地域外からの集客にもつながります。
さらに、PayPayは加盟店側にも販促用のポスターやステッカーを無料提供しており、店頭に掲示するだけで「このお店はキャッシュレス対応している」という安心感を与えられます。加えて、SNSや自社サイトで「PayPay対応店」であることを発信することで、顧客の来店動機を高められます。
効果的な活用のコツは、キャンペーン期間を事前に把握し、在庫や仕入れを調整すること。そして、キャンペーン開始直後に積極的な告知を行い、一気に集客する戦略です。
手数料・振込サイクルの特徴
PayPayの導入を検討する際、多くの個人事業主が気になるのが「手数料」と「入金サイクル」です。2021年10月までは決済手数料が無料でしたが、現在は原則として決済手数料は1.60%(または1.98%)に設定されています。クレジットカード決済の手数料が3〜5%程度であることを考えると、比較的低コストで利用できる点は魅力です。
入金サイクルについては、PayPay銀行を利用すれば最短翌日入金が可能で、さらに振込手数料も無料です。これにより、キャッシュフローが安定しやすく、小規模事業者にとって大きなメリットになります。もし他の銀行口座を利用する場合は、入金は月1回で、振込手数料が発生します。特に売上の回転が早い業種ではPayPay銀行の口座開設が事実上の必須といえます。
また、売上や振込履歴はオンラインでリアルタイムに確認できるため、日々の収支管理や在庫調整にも役立ちます。手数料率が低く、入金も早いことは事業の安定に直結するため、特に現金商売が中心だった個人事業主にとっては大きな転換点になるでしょう。
ただし注意点として、キャンセルや返金が発生すると、その分の売上は差し引かれ、手数料は返金されないケースがあります。この点は導入前に必ず理解しておき、返金ポリシーを明確にしておくことが大切です。
デメリットやリスクも
PayPay導入には多くのメリットがありますが、当然ながらデメリットやリスクも存在します。まず、ネット環境やアプリの不具合による決済トラブル。通信障害が起きると決済ができず、販売機会を逃す可能性があります。このため、非常用として現金決済を残しておくのがおすすめです。
次に、利用者の層によってはまだキャッシュレスに抵抗を持つ人も一定数存在します。特に高齢者や現金主義の顧客が多い地域では、導入直後は利用率が伸び悩む場合があります。
さらに、手数料はクレジットカードより低いとはいえ、現金決済に比べれば確実に利益が削られます。少額商品を大量に販売するビジネスモデルの場合は、手数料負担が重くならないよう価格設定の見直しが必要です。
また、PayPay残高払いでは売上入金までタイムラグがあるため、即日現金化はできません。短期的な資金繰りが厳しい事業者はこの点も考慮する必要があります。
最後に、加盟店審査に落ちる可能性もゼロではありません。特に開業届なし・実店舗なしの場合は、事業性を証明する資料をしっかり用意して臨むことが重要です。
PayPayをビジネスに導入するならこちら!
開業届なしでもPayPay導入できる業種とできない業種
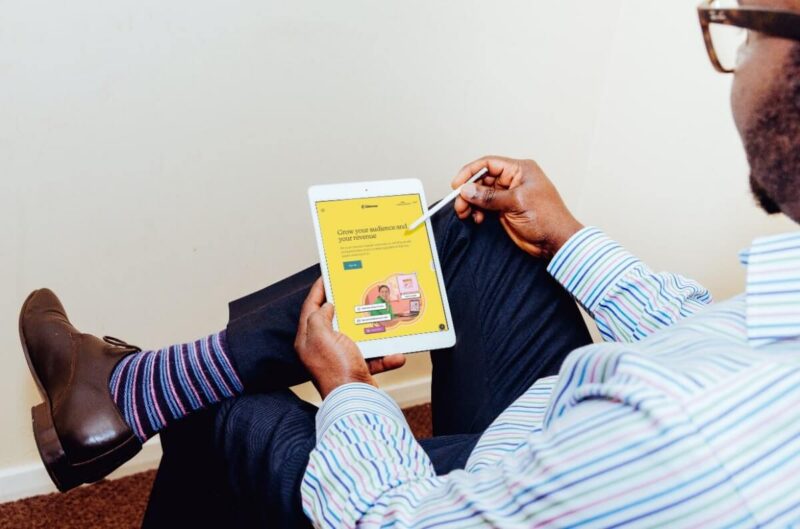
・ネット販売のみのケース
・店舗なしでの利用事例
・フリーランスでの導入可否
・イベント出店時の利用
・審査に通りやすい業種・通りにくい業種
ネット販売のみのケース
開業届を出していない個人でも、ネットショップ運営者はPayPay導入が可能な場合があります。特に、BASEやSTORESなどのECプラットフォームを利用している場合、PayPay連携機能を通して決済を受け取ることができます。この場合、PayPay加盟店審査では、開業届の代わりにショップURLや販売実績のスクリーンショットを提出することで、事業性を証明することが可能です。
ただし、ネット販売のみであっても、販売する商品やサービスの種類によっては導入が難しい場合があります。例えば、成人向けコンテンツや高リスク商品(タバコ、酒類など)を扱う場合は、PayPay側で利用制限や審査落ちになる可能性が高まります。
また、実店舗を持たないネット販売では、顧客との直接対面がないため、PayPayのQRコード決済よりも「オンライン決済リンク」を使った取引が中心になります。この場合は、PayPay加盟店アカウントの設定方法が異なるため、公式の案内に沿って正しく登録する必要があります。
つまり、ネット販売は開業届なしでも導入しやすい分野ですが、商品ジャンルや販売形態に注意が必要です。さらに、ショップの信頼性を高めるためにも、購入者からのレビューやSNSでの活動実績を積み上げておくことが、審査通過率アップのポイントになります。
店舗なしでの利用事例
実店舗がなくても、PayPayを導入している個人事業主は増えています。代表的なのは、出張型サービス業やイベント出店型のビジネスです。例えば、ハンドメイド作家がマルシェやフリーマーケットで販売するケース、美容師が出張カットを提供するケースなどでは、PayPayのQRコードを印刷して持ち運ぶだけで決済が可能になります。
店舗なしの場合、審査で重要視されるのは「事業活動を証明できる資料」です。これには、イベント出店の案内チラシや、サービス紹介のWebページ、過去の活動写真などが有効です。また、SNSでの告知や販売実績も加点要素になります。
一方で、完全に個人の趣味レベルでの活動や、事業性が不明確な場合は審査が通らないことがあります。このため、開業届がなくても、事業として活動していることを明確に示すことが何より大切です。
店舗なしのメリットは、場所代がかからない分、低コストでビジネスを展開できる点です。そこにPayPayを組み合わせれば、現金のやり取りや釣り銭準備の手間を省き、効率的に販売できます。特に野外イベントや臨時出店の場面では、キャッシュレス対応が顧客満足度を高める大きな要素になります。
フリーランスでの導入可否
フリーランスとして活動している人は、開業届がなくてもPayPayを導入できる可能性があります。例えば、ライター、カメラマン、デザイナー、家庭教師などの業種は、物販だけでなくサービス提供でもPayPayの決済を受け付けられます。審査時には、ポートフォリオや過去の取引実績、サービス内容がわかるWebサイトやSNSのURLを提出すると通りやすくなります。
特に対面でサービスを提供するフリーランス(例:ヨガインストラクターやセミナー講師)は、QRコードを印刷して持参すればその場でスマホ決済が可能です。顧客側もアプリで即時に支払いが完了するため、現金を用意する必要がなく、支払いのスムーズさから顧客満足度が向上します。
ただし、業種によってはPayPayが禁止しているカテゴリー(金融サービスや投資関係など)に該当する場合があるため、事前に利用規約を確認することが重要です。また、継続的に取引する場合は、会計処理や確定申告を見据えて取引記録をしっかり残すことが必要です。
フリーランスの強みは、実店舗や在庫が不要で、サービスの質とスピードで勝負できることです。そこにPayPayを組み合わせることで、現金管理の負担を減らし、顧客の利便性を高めることができます。特にリピーターの多い業種では、キャッシュレス対応が信頼感の向上にもつながります。
イベント出店時の利用
イベントやフェス、マルシェ、展示会などの場では、PayPayは非常に有効な決済手段です。出店者にとっては、現金のやり取りが不要になり、盗難や釣り銭不足のリスクを大幅に減らせます。また、PayPayは通信環境さえあれば即日導入可能なため、期間限定の出店でも対応しやすい点が魅力です。
イベント出店では、QRコードを立て看板やレジ周辺に掲示しておくだけで決済可能。さらに、PayPayのキャンペーン期間とイベントが重なると、集客効果は飛躍的に高まります。実際に「地域振興キャンペーンと同時に出店したところ、現金払いの倍以上がPayPay決済だった」という事例もあります。
ただし、屋外イベントの場合は通信環境が安定しないケースもあるため、モバイルWi-Fiやスマホの通信プランを確認しておくことが重要です。また、顧客にとって「PayPayが使える」という情報は来場動機になり得るため、事前告知をSNSや出店案内ページに記載すると効果的です。
イベント出店は、一度に多くの新規顧客と接点を持てる場です。そこでスムーズな決済体験を提供できれば、後日のリピーター化にもつながります。
審査に通りやすい業種・通りにくい業種
PayPayの加盟店審査は、業種によって通りやすさが異なります。一般的に、物販や飲食業、サービス業(美容室、整体、教育サービスなど)は審査に通りやすい傾向があります。特に、店舗や販売実績、サービス提供の証拠が明確な業種は、開業届がなくても審査を突破できる可能性が高いです。
一方で、通りにくい業種も存在します。代表的なのは、金融関連(投資、保険、融資など)、アダルトコンテンツ、違法性が疑われる商品やサービスを扱う業種です。また、高額商品を取り扱う業種(宝飾品、骨董品など)も、不正利用やマネーロンダリング防止の観点から審査が厳しくなります。
また、オンラインのみで運営する事業の場合、事業の信頼性を証明する資料が乏しいと審査落ちの可能性が高まります。この場合は、WebサイトやSNSでの販売実績、顧客からのレビュー、出店イベントの記録などを積極的に提示することが有効です。
開業届なしでの導入を目指す場合は、業種選びと事業の見せ方が非常に重要です。安全性や信頼性をアピールできる資料を整えることで、審査の通過率を上げることが可能です。
PayPayをビジネスに導入するならこちら!
PayPay導入から確定申告までの流れ
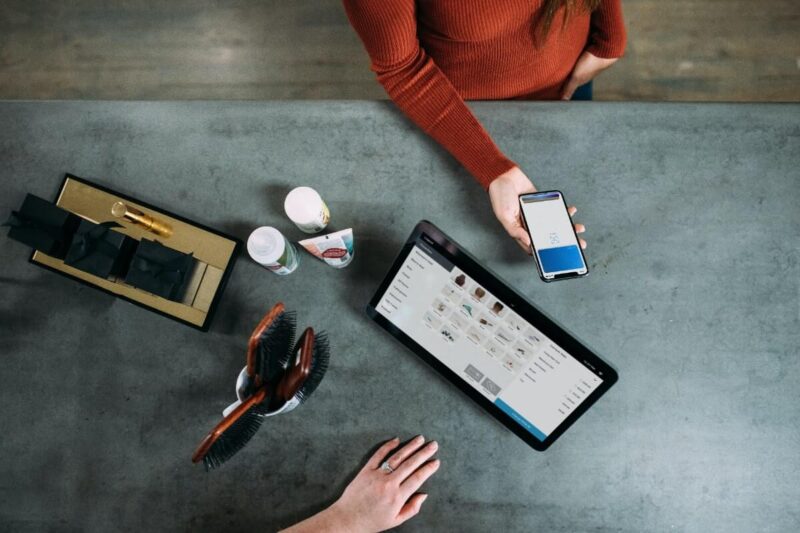
・売上データの確認方法
・確定申告に必要なデータの準備
・開業届なしの場合の申告方法
・収支管理のコツ
・会計ソフトとの連携方法
売上データの確認方法
PayPayでは、加盟店管理画面(PayPay for Business)から売上データをリアルタイムで確認できます。取引日、決済金額、支払い方法、返金状況などが一覧で表示され、日別・月別での集計も簡単です。これにより、日々の売上管理や在庫調整がスムーズに行えます。
さらに、売上データはCSV形式でダウンロード可能なため、会計ソフトやExcelに取り込んで経理処理に活用できます。特に確定申告時には、売上記録の全データを一括出力しておくことで、帳簿付けが格段に効率化されます。
重要なのは、現金売上とPayPay売上を分けて記録することです。混同すると会計処理が複雑になり、税務署から指摘を受ける可能性があります。また、返金処理やキャンセル分も正確に記録しておくことが必要です。
PayPayの強みは、現金取引に比べて記録の正確性が高い点です。現金では「記録漏れ」が起きやすいですが、PayPayでは自動的にデータが残るため、確定申告の際に証拠資料としても有効に活用できます。
確定申告に必要なデータの準備
確定申告では、PayPayの売上データと経費データをまとめて提出できる形にしておく必要があります。売上データはPayPay for BusinessからダウンロードしたCSVファイルを活用し、期間を「申告対象年(1月1日〜12月31日)」に設定して抽出します。
経費については、PayPay売上に直接関連する仕入れや設備費、人件費、交通費などを領収書や請求書と一緒に保管します。電子データでも保存可能ですが、税務署の求めがあれば提示できるよう整理しておきましょう。
特に開業届を出していない場合でも、一定額以上の所得があれば確定申告義務が発生します。このため、売上データは必ず月ごとに整理しておくのがベストです。また、消費税の課税事業者に該当する可能性がある場合は、売上総額だけでなく、非課税取引や軽減税率対象売上も区別して記録しておく必要があります。
帳簿を正確につけておけば、青色申告への切り替えや事業拡大時の融資申請にも有利に働きます。PayPayの売上管理機能は、その土台作りに最適です。
開業届なしの場合の申告方法
開業届を提出していない状態でも、PayPayでの売上があれば確定申告は必要です。基本的には「白色申告」として扱われます。白色申告は青色申告より帳簿付けの要件が緩く、複式簿記も不要ですが、経費の計上や収支の把握は正確に行わなければなりません。
申告方法は以下の流れです。
PayPayの年間売上データをダウンロード
現金売上や他の決済手段の売上と合算
経費データを集計(領収書・請求書の整理)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力
e-Taxまたは税務署窓口から提出
開業届を出していないと青色申告の特典(最大65万円の控除や赤字繰越)が使えません。そのため、売上が安定してきたら早めに開業届を提出し、翌年から青色申告に切り替えるのが有利です。
また、副業としてPayPay売上がある場合も、給与所得以外の所得が20万円を超えると申告義務が発生します。これは会社員やパートでも同じです。逆に20万円未満の場合は所得税の申告義務はありませんが、住民税は申告が必要な場合が多いため、市区町村役場への確認が必須です。
開業届なしでも申告は可能ですが、税務リスクを減らすためには、帳簿の整備と収支管理を日常的に行うことが重要です。
収支管理のコツ
PayPayを使った事業では、売上と経費を常に明確に分けて記録することが収支管理の基本です。特に個人事業主の場合、生活費と事業資金を混同しがちですが、これを避けるためには専用の銀行口座を用意するのが理想的です。
PayPay銀行を売上入金専用にすれば、売上と私的入出金を自動的に分けやすくなります。また、売上データは毎月CSVでダウンロードし、会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)に取り込むと効率的です。
経費は領収書をスキャンしてクラウド保存する方法がおすすめです。紙のまま保管するよりも探しやすく、税務調査時にもすぐ提示できます。さらに、月ごとに売上と経費を比較して利益率を確認すると、経営改善のヒントが見えてきます。
PayPayの利用履歴は取引の証拠になるため、現金売上よりもトラブル防止効果が高いです。この利点を活かし、定期的にデータを見直すことで、事業の健全性を保つことができます。
会計ソフトとの連携方法
PayPayの売上データは、会計ソフトと連携させることで日々の記帳作業を大幅に効率化できます。多くのクラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードクラウド、弥生オンラインなど)は、CSVファイルのインポート機能を備えており、PayPay for Businessからダウンロードした取引データをそのまま取り込めます。
連携手順は以下の流れが基本です。
PayPay for Businessにログイン
対象期間の売上データをCSVでダウンロード
会計ソフトの「取引インポート」機能を開く
CSVをアップロードし、取引内容を勘定科目に自動振り分け
必要に応じて勘定科目や摘要を修正して登録
これにより、手入力による記帳ミスや漏れを防げます。また、会計ソフトによっては銀行口座やクレジットカードと同様にPayPay口座の明細を自動取得できる場合もあります。この場合、手動ダウンロードすら不要になり、ほぼリアルタイムで帳簿が更新されるため、経理作業が格段に楽になります。
さらに、クラウド会計を利用すれば、スマホやタブレットからもデータ確認や仕訳登録が可能です。特に出張やイベント出店が多い事業者にとっては、外出先でも売上管理ができるのは大きなメリットです。
会計ソフト連携は、確定申告時の効率化だけでなく、日常的な経営判断のスピードアップにもつながります。
PayPay導入時の審査ポイントと対策

・審査に必要な書類一覧
・住所・身分証明の注意点
・ビジネスモデルの説明方法
・審査落ちしやすいパターン
・審査通過率を上げるための工夫
・この記事のまとめ
審査に必要な書類一覧
PayPay加盟店登録を行う際には、事業内容を証明できる書類が必要です。開業届がない場合でも、以下のいずれかを提出すれば審査が進むことがあります。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
事業活動を示す資料(WebサイトURL、SNSアカウント、チラシ、パンフレット)
商品・サービスの写真やメニュー表
イベント出店許可証や契約書などの活動証拠
これらは、事業が実在し、継続的に運営されていることを裏付ける重要な要素です。特に開業届なしの場合は、資料の充実度が審査通過のカギになります。
住所・身分証明の注意点
審査では、提出する身分証明書の住所と申請フォームの住所が一致している必要があります。もし異なる場合は、公共料金の領収書や住民票などの補足資料を求められることがあります。また、住所の番地や建物名は省略せず、公式な記載通りに入力することが大切です。
特にマンションやアパートの場合、部屋番号を省略すると住所不一致で審査がストップするケースがあります。
ビジネスモデルの説明方法
実店舗がない事業者は、ビジネスモデルの説明が不十分だと審査に落ちやすくなります。申請時には「どのような商品・サービスを、どんな方法で販売しているのか」を具体的に記載することが重要です。
例えば、「ハンドメイドアクセサリーをオンラインショップとマルシェイベントで販売」や「出張型ネイルサービスを自宅訪問で提供」など、事業の形がイメージしやすい説明が効果的です。
審査落ちしやすいパターン
以下の条件に当てはまると審査が厳しくなります。
高額商品のみを扱っている
成人向けコンテンツを販売している
事業のWeb情報が全くない
過去にPayPayや他の決済サービスで規約違反をしたことがある
こうした場合は、代替商品を提示したり、事業の透明性を高める工夫が必要です。
審査通過率を上げるための工夫
SNSやWebサイトで事業活動を継続的に発信
商品・サービスの写真を豊富に用意
直近の販売実績やイベント参加履歴を提出
住所や連絡先などの情報を正確に記載
審査は「事業の信頼性」を確認する作業なので、情報の量と正確さが重要です。
PayPayをビジネスに導入するならこちら!
「PayPayは開業届なしでも使える?個人事業主の導入メリットと注意点を解説!」のまとめ
開業届を提出していなくても、PayPayは事業性を証明できる資料さえあれば導入が可能です。特にネット販売やイベント出店、フリーランスのサービス提供などは、実績や活動証拠を用意することで審査を通過しやすくなります。
PayPay導入の最大の魅力は、キャッシュレス決済の利便性と集客効果です。特に若年層やスマホ世代は現金を持ち歩かない傾向が強く、対応店舗であること自体が顧客獲得のきっかけになります。加えて、全国的・地域的なキャンペーンを活用すれば、短期間で売上を大きく伸ばせるチャンスもあります。
一方で、手数料や通信障害、顧客層による利用率の差など、デメリットも存在します。そのため、導入前に事業形態や顧客属性を分析し、必要に応じて現金決済も併用することが望ましいです。
また、確定申告の際には、PayPay売上を含めた全収支を正確に記録しておくことが重要です。会計ソフトとの連携やCSVデータ活用で、帳簿管理は大幅に効率化できます。
今後、キャッシュレス化はますます加速していきます。開業届がなくても、しっかり準備と情報発信を行えば、PayPayは小規模事業者や個人事業主の大きな武器となるでしょう。



