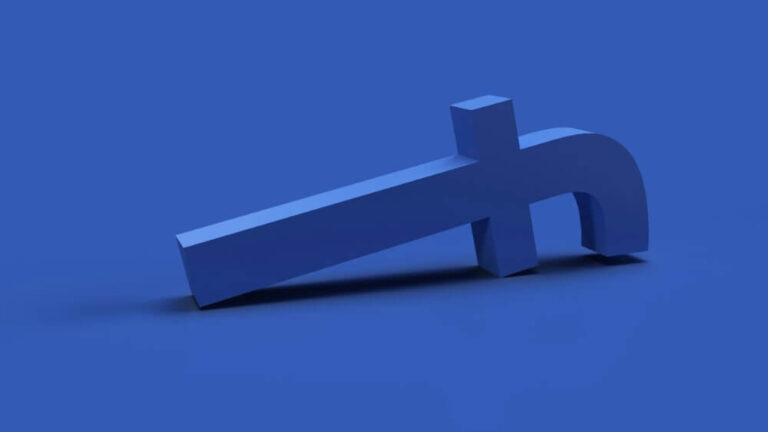「Facebookってもうオワコンでしょ?」そんな声を耳にしたことはありませんか?かつてSNSの王様とも言われたFacebookも、時代の移り変わりとともにその存在感が薄れてきたように感じる人も多いはずです。特に若い世代を中心に、InstagramやTikTokに流れていく中で、Facebookは“時代遅れ”のイメージを持たれがちです。
ですが、本当にFacebookはもう終わってしまったのでしょうか?この記事では、「オワコン」と言われる背景を掘り下げつつ、それでもなお利用され続けている理由や、今こそ注目したい使い方を徹底的に解説していきます。読み終えた頃には、きっとあなたもFacebookの「新しい可能性」に気づくはずです。
Facebook離れが止まらない?数字で見るユーザーの推移

・若いユーザーの激減
・アクティブユーザー数の推移
・なぜZ世代はFacebookを使わないのか?
・ビジネス活用も減少傾向?
・日本と海外のFacebook利用動向の違い
若いユーザーの激減
Facebookが「オワコン」と言われる大きな理由のひとつが、若者ユーザーの大幅な減少です。特にZ世代(1990年代後半〜2010年生まれ)は、FacebookではなくInstagramやTikTokなどのビジュアル重視型SNSに移行しています。背景には、「親世代が使っているSNSは恥ずかしい」「リアルな人間関係の距離が近すぎて使いづらい」といった感情があります。Facebookは実名制のSNSであり、学校や職場、家族などリアルなつながりが強調されるため、自由な表現がしにくいと感じる若者が多いのです。加えて、ニュースフィードのアルゴリズムが複雑で、見たい投稿よりも広告や企業の投稿が目立ってしまう点も、若年層離れを加速させています。こうした傾向は日本だけでなく、アメリカやヨーロッパなど世界中で見られる現象で、Facebook自体も若年層向けのテスト機能を導入するなど対策を行っていますが、抜本的な解決には至っていません。
アクティブユーザー数の推移
Facebookのアクティブユーザー数(MAU=月間アクティブユーザー)は、世界的には依然として20億人を超える巨大なプラットフォームですが、成長率には明らかに鈍化が見られます。特に先進国ではユーザー数が横ばい、もしくは減少に転じている地域もあります。2022年にはFacebookが初めてユーザー数の減少を公式に発表し、大きな話題となりました。この発表は「SNSの王者」であったFacebookが岐路に立たされている象徴的な出来事でした。一方で、東南アジアやアフリカなど新興国では利用者がまだ増えており、Facebookとしてもこうした地域に注力している状況です。ユーザー数の推移を読み解くことで、今後の戦略やサービスの進化が見えてくるかもしれません。
なぜZ世代はFacebookを使わないのか?
Z世代がFacebookを避ける理由は、「情報過多」と「共感の薄さ」にあります。InstagramやTikTokのように感覚的に楽しめるコンテンツとは異なり、Facebookは文章中心で、情報が多すぎて読むのに疲れてしまうという声もあります。また、投稿へのリアクションが「いいね」やコメントに限られており、エンタメ性が低いのも要因のひとつです。Z世代は「見て楽しむ」「笑える」「共感できる」コンテンツを求めていますが、Facebookはそれに応えきれていません。さらに、ストーリーズやリールといった機能も後発で、他のSNSと比べると遅れている印象があります。Z世代にとってFacebookは、あくまで「昔のSNS」「親が使うもの」という位置づけになっており、イマドキの使い方にはマッチしていないのです。
ビジネス活用も減少傾向?
かつては企業のマーケティングやブランディングに欠かせない存在だったFacebookも、最近ではその役割が薄れてきています。特に日本国内ではFacebookページの更新頻度が落ちており、「更新が止まっているページ」が増えてきている印象です。理由としては、投稿のリーチ率が下がり、広告を出さないと見られないという現実があります。これは中小企業にとってコスト面での負担が大きく、他の無料で伸びやすいSNSに移行する企業が増えているのです。また、動画コンテンツが主流となる中で、Facebookの投稿形式は柔軟性に欠け、特に若年層に向けたプロモーションには不向きとされています。企業のSNS運用担当者の中には、「Facebookはとりあえず更新しておくけど、メインはInstagramやX(旧Twitter)」という声も少なくありません。
日本と海外のFacebook利用動向の違い
Facebookの「オワコン度」は国によって異なります。日本では特に若者を中心に利用者が減少している一方、アメリカやヨーロッパではまだ日常的に使っている中高年層も多く存在します。また、東南アジアではFacebookがインターネットそのもののように使われており、メッセンジャーやマーケットプレイスなど多機能SNSとして重宝されています。日本ではLINEが主な連絡ツールであるため、Facebookメッセンジャーの使用率も低く、結果的に利用頻度がさらに下がっているのです。国や文化によって使い方が異なるため、「日本でオワコン」とされても、世界的には依然として存在感のあるSNSということになります。利用動向の違いを理解することで、どこで何が有効かを見極めるヒントになります。
Facebook運用ならSocialDogがおすすめ!
・複数のSNSを一括管理
・データ分析機能が充実
・予約投稿で運用を効率化
・簡単登録&無料トライアルあり
→SocialDogでFacebookを効率的に運用しよう!
Facebookが「オワコン」と言われる理由は?

・オワコンという言葉の意味
・SNSとしての魅力が減った?
・UIの古さと使いにくさ
・広告重視の姿勢がユーザー離れを招いた?
・競合SNSとの機能比較
オワコンという言葉の意味
「オワコン」という言葉は、「終わったコンテンツ」の略語で、もともとはネットスラングとして誕生しました。主にアニメやゲーム、芸能人などの人気が急激に落ち込んだときに使われる表現ですが、近年ではSNSやアプリ、企業に対しても使われるようになりました。つまり、かつては注目されていたが、今は話題性や必要性がなくなったものに対して使われます。Facebookに対してこの言葉が使われる理由は、「以前ほどの勢いがない」「若者に使われていない」「流行遅れ」といったイメージがあるからです。しかし、この「オワコン」という言葉には、実は感覚的な印象や噂も多く含まれており、必ずしも現実の数字やデータに基づいた評価とは限らないことも理解しておく必要があります。
SNSとしての魅力が減った?
Facebookが「オワコン」と呼ばれる背景には、かつてのようなSNSとしてのワクワク感や魅力が薄れてきたことが挙げられます。10年以上前、Facebookが日本で話題になり始めた頃は、「実名でつながれる新しいSNS」として注目され、リアルな人脈の拡大ツールとして一躍人気を博しました。しかし、今ではInstagramやTikTokのように、感覚的に楽しめるSNSが主流になっており、Facebookの投稿文化は「真面目すぎる」「堅苦しい」「見ていて疲れる」と感じられることも多くなっています。さらに、タイムラインに表示される情報が多すぎて、必要な投稿が埋もれてしまうという問題もあり、使いにくさが目立つようになっています。結果として、ユーザーにとって「楽しめる場所」ではなく、「見るだけで疲れるSNS」になってしまっているのです。
UIの古さと使いにくさ
Facebookのユーザーインターフェース(UI)は、度重なるアップデートで少しずつ変化してきたものの、他のSNSと比べるとやや古臭い印象を持たれがちです。特にスマホアプリでは、情報量が多すぎてどこに何があるのかわかりにくい、という声も少なくありません。画面上にはニュースフィード、ストーリーズ、グループ、マーケットプレイス、メッセンジャーなど多数の要素が詰め込まれており、シンプルな操作性を好む若年層にとっては「ごちゃごちゃして使いにくい」と感じられることが多いのです。対照的に、TikTokやInstagramは非常にシンプルな操作で直感的に使える設計になっており、その差がユーザーの移行を加速させています。UIの改善が遅れていることも、「オワコン」と呼ばれる一因と言えるでしょう。
広告重視の姿勢がユーザー離れを招いた?
Facebookの収益モデルは基本的に広告で成り立っており、アルゴリズムの変更もそれに最適化されてきました。結果として、ユーザーが見たい友人の投稿よりも、広告や企業のコンテンツが優先的に表示されるようになり、ユーザー体験が悪化しています。特に2020年以降は広告表示の頻度が高まり、スクロールするたびに広告が目に入るという状況になっています。これにより、「Facebookはもう友達とつながる場所ではなく、広告を見る場所になった」というネガティブな印象を持つ人が増えました。実際に、Facebookを開く頻度が減ったというユーザーの多くが「見たい情報が出てこない」と感じており、広告の存在がFacebook離れを助長しているのです。
競合SNSとの機能比較
Facebookは多機能なSNSですが、その「多機能さ」がかえってユーザーにとっては煩雑に感じられてしまっています。たとえばInstagramは写真・動画投稿に特化し、TikTokは短い動画をテンポよく楽しむことができます。Twitter(X)はリアルタイムの情報収集に強く、ThreadsやLinkedInも目的に応じた使い分けができるため、特化型SNSの方が人気を集めています。一方Facebookは、すべてを一つにまとめた「万能型SNS」としての性格が強く、逆にそれが中途半端になってしまっている印象を与えています。若いユーザーにとっては、「写真ならインスタ」「動画ならTikTok」と用途がはっきりしている方が使いやすく、Facebookは「何をするSNSなのかわかりにくい」というイメージを持たれてしまっているのです。
Facebookは終わってない!まだまだ使える5つの理由

・Facebookグループの活用法
・中高年層ユーザーの強い支持
・イベント機能の便利さ
・グローバルなビジネスではまだまだ現役!
・広告運用の精度は今でもトップレベル
Facebookグループの活用法
Facebookの中でも、今なお活発に使われている機能のひとつが「Facebookグループ」です。これは共通の趣味や関心を持った人たちが集まり、情報交換や相談、イベントの告知などを行えるコミュニティ機能です。たとえば、フリーランス同士がノウハウを共有したり、子育て中の親たちが地域情報を交換したり、同業者が最新ニュースを話し合う場所として活用されています。SNSの中でもグループ機能がここまで柔軟で充実しているのはFacebookだけといっても過言ではありません。また、投稿に対してコメントだけでなくファイル添付やアンケートの実施もできるため、ビジネスや教育の現場でも重宝されています。特定のテーマに沿ったやりとりができるため、タイムラインのような「ノイズ」が少なく、目的に応じた深い交流が可能です。こうした活用法により、Facebookは「表向きのSNS」としてではなく「実務で役立つツール」としての価値を維持しています。
中高年層ユーザーの強い支持
Facebookの主な利用者層が20代から離れつつある一方で、40代〜60代の中高年層からは今でも根強い支持を得ています。これは他のSNSと比較して、実名でつながる信頼性の高さや、投稿が長文でも読んでもらえる文化が定着していることが理由です。中高年層はTwitterやInstagramのような「短文・瞬間消費型コンテンツ」よりも、しっかりと内容を読み、意見を交わすことを好む傾向があります。そのため、Facebookの投稿形式が年齢層にマッチしており、家族や旧友とのつながりを保つ場として定着しているのです。また、PC操作に慣れた層にとって、Facebookのデスクトップ版は使いやすく、情報のシェアやコメントもしやすい設計になっています。若者離れが話題になる中で、中高年層がFacebookのコアユーザーとして支え続けているという事実も見逃せません。
イベント機能の便利さ
Facebookの「イベント機能」も見逃せないポイントです。オフラインでもオンラインでも、誰でも簡単にイベントを作成し、参加者を募ることができます。たとえば、勉強会、セミナー、地域のお祭り、ライブ配信、Zoomイベントなど、あらゆるジャンルに対応しており、リマインダー機能や出欠確認も非常にスムーズです。さらにイベントページでは、投稿や写真、動画なども共有でき、イベント前後のコミュニケーションも取りやすい設計になっています。特にリアルイベントの主催者や講師、地域活動のリーダーたちには、この機能が「無料で使える集客・管理ツール」として高く評価されています。他のSNSにはこのような本格的なイベント機能が少なく、Facebookがビジネスや地域活動における「実務の場」として支持され続けている理由の一つです。
グローバルなビジネスではまだまだ現役!
Facebookはグローバルに展開されているSNSのため、海外とのビジネスでも非常に有効です。特に東南アジアや南米などの国々では、Facebookがインターネットの入り口のような存在となっており、企業ページやMessengerを使った問い合わせ対応などが一般的です。そのため、日本国内では見えにくいものの、海外展開をしている企業や、外国人観光客を対象としたビジネスでは、Facebookの存在感はまだまだ大きいのが現実です。実際に、観光業界や国際貿易、語学教育などの分野では、Facebook経由での情報発信や顧客対応が日常的に行われています。世界基準で見ると、Facebookは今でも「最も信頼されるビジネスSNS」としての役割を果たしているのです。
広告運用の精度は今でもトップレベル
「Facebook広告はもう効果がない」と思われがちですが、実際にはその広告運用の精度は今でも業界トップクラスです。特に「ターゲティングの精度」においては、ユーザーの興味・関心、年齢、性別、居住地、過去の行動などをもとに、非常に細かく配信設定が可能です。広告を出す側にとっては、無駄なコストを省きつつ、狙った層に効率よくアプローチできるメリットがあります。また、Instagramと広告システムが連携しており、1回の広告設定で複数プラットフォームに配信できるという利便性も魅力です。中小企業や個人事業主にとっては、限られた予算でも高い成果が期待できるツールであり、「オワコン」と呼ぶにはもったいないほどの実力を持っています。うまく使えば、今でも強力な武器となることは間違いありません。
個人もビジネスも!Facebookのこれからの使い道

・個人の日記や記録ツールとしての活用
・コミュニティマーケティングへの活用法
・Facebookページでの情報発信のコツ
・広告を使わずにリーチを伸ばす方法
・Instagramや他SNSとの連携
個人の日記や記録ツールとしての活用
Facebookはもともと「つながる」ためのSNSですが、現在では「自分の記録を残す場所」として使っている人も増えています。たとえば、旅行の思い出を写真付きで投稿したり、日々の気づきや考えを文章で残したりと、日記のように活用する使い方です。投稿は「非公開」や「友達限定」に設定することもできるため、安心してプライベートな記録を綴ることができます。また、過去の投稿が「○年前の今日」として自動で表示される「思い出機能」もあり、自分自身の歩みを振り返るツールとしても優秀です。スマホのメモ帳ではできない「ビジュアル+日付つきの記録」として活用できるため、自分だけのライフログを残すには最適です。SNSとしてだけではなく、「パーソナルメディア」としての活用が、今後の新たな価値となり得るでしょう。
コミュニティマーケティングへの活用法
近年注目されているマーケティング手法のひとつに「コミュニティマーケティング」があります。これは、顧客やファンとのつながりを深めながら、信頼関係を築いていくスタイルです。Facebookはこのスタイルにぴったりのツールです。Facebookグループを活用すれば、商品購入者だけの限定コミュニティを作ったり、興味関心の高い人を集めて情報交換ができたりします。グループ内ではライブ配信やアンケートも可能で、双方向のやり取りが活性化されやすい点が強みです。また、コメント欄のやり取りを通じてユーザーの声を拾いやすく、商品改善や新企画にもつなげることができます。インスタグラムのような「見るだけ」のSNSとは異なり、Facebookではユーザー同士の関係性が構築されやすく、顧客との継続的な関係性を築くための「濃い場」として非常に有効です。
Facebookページでの情報発信のコツ
ビジネス用途では、Facebookページを活用することで公式な情報発信が可能になります。ただし、以前のように「投稿すれば多くの人に届く」という時代は終わっており、今は戦略的に投稿内容を考える必要があります。効果的な情報発信のポイントは3つあります。1つ目は「ユーザーが共感しやすい内容を発信すること」。2つ目は「ビジュアル(写真や動画)を活用して目を引くこと」。そして3つ目は「コメントやリアクションへの返信を丁寧に行うこと」です。また、FacebookページはSEO対策にも効果があり、Google検索で企業名を調べた際に上位に表示されることも多いため、ブランドイメージの管理にも役立ちます。発信内容にひと工夫することで、Facebookページは今でも十分に活用価値のあるツールなのです。
広告を使わずにリーチを伸ばす方法
広告を出さなくてもリーチを伸ばす方法は、いくつか存在します。まず大切なのは「エンゲージメント率(反応の高さ)」を意識した投稿を行うことです。たとえば、ユーザーに質問を投げかけたり、意見を求める投稿を行ったりすることで、コメントやシェアが増えやすくなります。また、投稿時間にも工夫が必要です。一般的に平日の朝8時〜9時、または夜21時〜23時はアクティブユーザーが多いため、この時間帯を狙って投稿すると反応が増える傾向があります。さらに、動画コンテンツは静止画よりも表示される可能性が高く、特に「字幕付き動画」はスマホユーザーに好まれるためおすすめです。これらを組み合わせることで、広告に頼らずとも自然な形で投稿が広がっていく可能性が十分にあります。
Instagramや他SNSとの連携
FacebookはInstagramと同じMeta社が運営しており、アカウント連携が非常にスムーズです。たとえば、Instagramに投稿した写真をそのままFacebookにもシェアしたり、広告出稿時に両方のプラットフォームに配信することが可能です。特にビジネス利用においては、両方のメディアを活用することでリーチを最大化することができます。また、最近ではThreadsやWhatsAppなどMeta関連のサービスとの連携も進んでおり、今後はさらに一体感のあるSNS運用が可能になるでしょう。さらに、X(旧Twitter)やLINEなどと併用することで、それぞれのプラットフォームの特性を生かしたクロスチャネルマーケティングも実現できます。「Facebook単体で完結させる」のではなく、「他SNSとのハブ」として活用することで、より戦略的な情報発信が可能になります。
Facebookが「オワコン」と言われながらも残り続ける理由
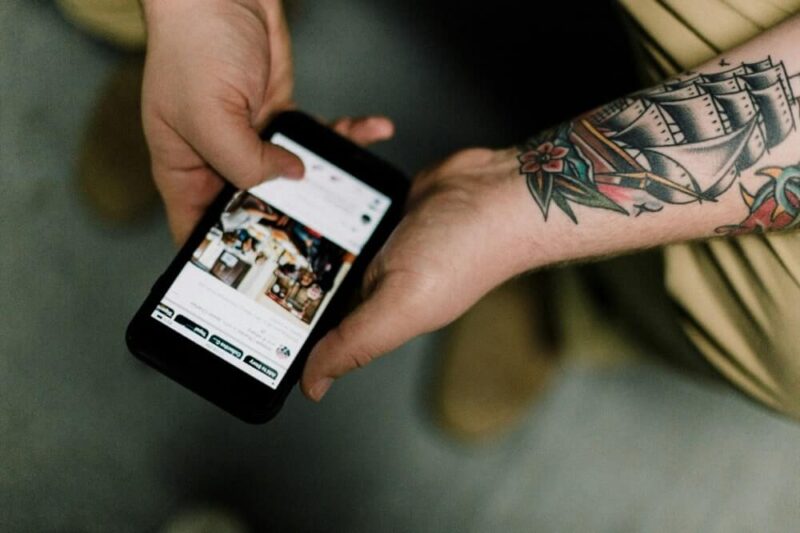
・「オワコン」でもニーズがある?
・テクノロジー企業としてのFacebook(Meta)の動向
・メタバースとの関係性と将来性
・ユーザー層の再定義がカギ?
・使い方次第で「オワコン」にはならない
・Facebook運用を効率化させるならSocialDogがおすすめ!
・この記事のまとめ
「オワコン」でもニーズがある?
「Facebookはもう使っていない」「オワコンだ」と言われる一方で、実際にはまだまだ日常的に使っている人が大勢います。特に中高年層や海外ユーザー、ビジネスユーザーにとっては、今でも欠かせないプラットフォームです。つまり、「全員が使わなくなったわけではない」というのが現実なのです。SNSの世界では、「トレンドから外れた=即オワコン」とされがちですが、利用され続けている限り、本当の意味での終わりとは言えません。実際に、ニュースやコミュニティ、イベント告知など、日常の中で役立っている場面も多く、「必要な人には今でも必要」な存在となっています。これは、Facebookが単なる流行りのSNSではなく、ある種の「社会インフラ」のような位置づけに進化しているとも言えるのです。
テクノロジー企業としてのFacebook(Meta)の動向
Facebookの運営元であるMeta社は、もはや「ただのSNS会社」ではありません。AI、VR、AR、そしてメタバースといった次世代技術への投資を積極的に行っており、企業としての成長は今も続いています。たとえば、Meta Quest(旧Oculus)シリーズを通じたVRの普及活動や、ビジネス向けの仮想空間構築など、SNSの枠を超えた取り組みが注目を集めています。つまり、Facebook単体の人気が落ち着いてきたとしても、会社としては未来を見据えてしっかりと舵を切っているのです。これらの動きは、いずれFacebook本体にも何らかの形でフィードバックされ、再び注目される可能性も十分にあります。「オワコン」どころか、進化の途中と言えるのではないでしょうか。
メタバースとの関係性と将来性
Meta社が注力している次世代技術の代表が「メタバース」です。Facebookというブランドから社名を「Meta」に変えたことからも、この方向にかける意気込みが伝わってきます。現時点ではメタバース市場自体がまだ黎明期ですが、将来的には仕事、遊び、学びの場として大きく発展していく可能性があります。そのとき、Facebookで築いたネットワークや実名ベースのつながりが、仮想空間上での信頼関係に変わるかもしれません。特にビジネス系メタバース空間では、「実名でのつながり」が前提となる場面も多く、Facebookの基盤が活きる可能性があります。つまり、Facebookは過去の遺産ではなく、未来への足場として生まれ変わる可能性を秘めているのです。
ユーザー層の再定義がカギ?
Facebookの「終わった感」は、実は若者中心の視点で語られていることが多いです。しかし、SNSはそれぞれ対象ユーザーが異なります。TikTokはZ世代、Instagramは20代女性、LinkedInはビジネスパーソン、そしてFacebookは「中高年」「実名でつながりたい人」「地域密着の情報を求める人」など、しっかりとしたニーズが存在します。つまり、Facebookが今後も残り続けるためには、「誰にとって必要なSNSなのか?」という再定義が必要です。万人に使われなくても、特定の人たちにとって不可欠なSNSであれば、それはもう「オワコン」ではありません。ニッチでも確実な支持層を確保することが、今後の鍵となるでしょう。
使い方次第で「オワコン」にはならない
最後に言えるのは、「Facebookがオワコンかどうかは、使い方次第で決まる」ということです。確かに昔のような勢いはないかもしれませんが、情報発信、コミュニティ、イベント運営、マーケティング、個人の日記など、多彩な使い方ができるSNSであることは今も変わりません。ユーザー側が目的を明確にし、機能を上手に使いこなせば、Facebookは今でも十分に役立つツールとなります。SNSの価値は「流行っているか」ではなく、「自分にとって役立つか」で判断すべきです。そう考えると、Facebookは「終わった」のではなく、「変わった」と表現するのがより正確かもしれません。
Facebook運用を効率化させるならSocialDogがおすすめ!
Facebookを活用して集客やブランディングを強化したいけれど、「投稿の管理が大変」「フォロワーの反応がわからない」といった悩みを抱えていませんか?そんな方におすすめなのが、SNS運用を効率化できる「SocialDog」です。
SocialDogは、FacebookだけでなくX(Twitter)やInstagramのアカウントも1つのダッシュボードで管理できるため、複数のSNSを運用している企業や個人にも最適です。
さらに、SNSでは見えにくいデータを分析できるツールが充実しており、フォロワーのニーズを深く理解できます。たとえば、フォロワーの属性や投稿のエンゲージメント率を把握することで、より効果的なコンテンツ戦略を立てることが可能になります。
また、予約投稿機能を活用すれば、数日分の投稿をまとめてスケジュール管理できるため、日々の投稿作業に追われることもありません。特に「忙しくて毎日投稿するのが難しい」「効果的な投稿時間を知りたい」という方には大きなメリットです。
しかも、SocialDogは簡単10秒登録&7日間の無料トライアル付きなので、まずは気軽に試してみることができます。すでに100万以上のアカウントが利用している信頼性の高いツールなので、Facebook運用を本格的に効率化したいなら、ぜひ導入を検討してみてください!
→SocialDogでFacebookを効率的に運用しよう!
「Facebookはオワコン?今でも使える5つの理由を解説!」のまとめ
「Facebook=オワコン」と言われることが増えた昨今ですが、この記事を通して見えてきたのは、その評価が一面的であるということです。確かに若年層を中心にユーザー離れが進み、UIやトレンドとのズレが否定できない一方で、Facebookには今でも確かなニーズと独自の価値があります。特に、グループ機能やイベント、実名でのつながりをベースにした信頼性は他のSNSにはない強みです。また、中高年層の支持や、海外ビジネスでの活用、広告ターゲティングの精度の高さも注目すべきポイントです。
さらに、Meta社全体としては、AIやメタバースなど未来志向の技術開発を続けており、Facebookというブランドが形を変えて次のステージへ進もうとしているのも事実です。「オワコン」という言葉に惑わされず、目的やユーザー層に応じて賢く使えば、Facebookは今後も十分に活用できるツールであり続けるでしょう。